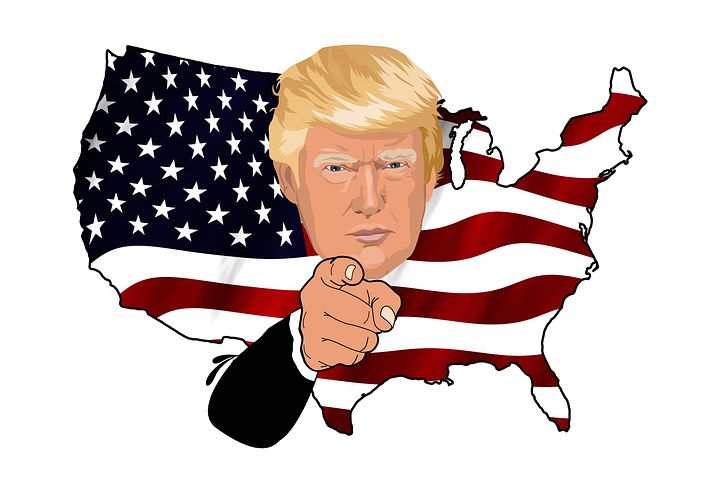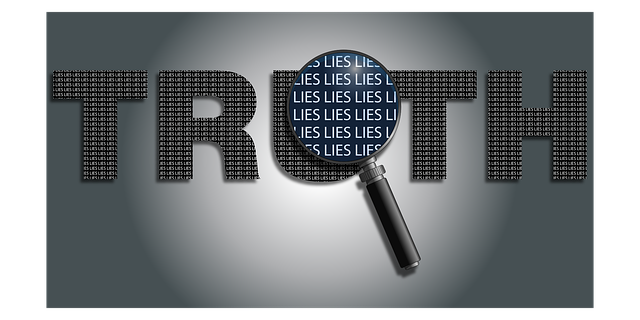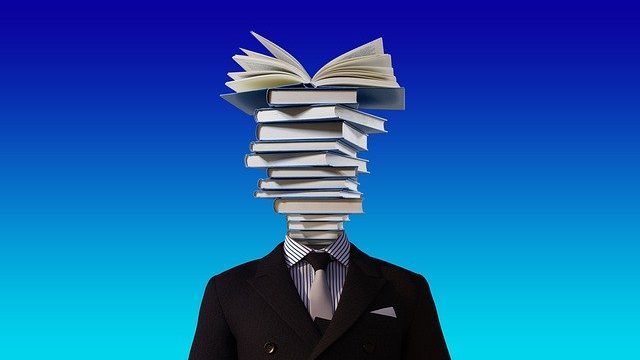こんにちは、セントです。
今回は、利下げをしたらどうなるの?というテーマで話をしていこうと思います。
投資初心者のときには、利上げとか利下げとか難しい言葉が多くて迷いがちですよね?
そして、FRBやECBがコロナウィルスの蔓延で利下げを実行しましたね。
FRB、ECB?なんだっけ?
わざと難しい言葉を使ってみたよ。
金融や投資の世界ではこんな「3文字英語の壁」にブチ当たるよね。
だから、難しい話は省いて説明するね。
「FRB」は日本における日銀と同じように、アメリカ(ドル)の金融政策などを決める機関なんだよ。
「ECB」はヨーロッパ(ユーロ)の金融政策を決めるところだよ。
日銀は、日本円の金融政策を決めてるもんね。
この動きから、なんとなく「経済を良くしようとするとき」に利下げを行うようですね。
ただ、仕組みがわからないと利上げがいいんだっけ?利下げがいいんだっけ?のようなよくわからない質問を続けてしまうことになります。
結論を言えば、利下げでも利上げでもメリットとデメリットがあるんだよということを深掘りして解説していこうと思います。
理解するためにはまずは、銀行の仕事について知らなくては説明しにくいので銀行の仕事から話していきますね。
それでは行ってみましょう。
銀行の仕事


銀行の仕事ってなんだと思いますか?
みんなから、お金を預かって大切に保管するのが仕事?
確かにそれも、大事な仕事なんですがメインの仕事はみんなのお金を利用してお金を貸し付けたり、投資をして利益を得るのが仕事なんですね。
借りたお金の金利よりも、高い金利で貸し出した場合に得ることのできる利益のことを利ザヤと言います。
銀行の大きな収入源のひとつです。
なんとなく、利下げに近づいてきてますね。
次は、「銀行の仕入れ」についてです。
銀行の仕入れ


銀行にも「仕入れ」があるんですよね。
結論を言えば、みんなから預かるお金が仕入れる商品ですよね。
八百屋では扱う商品は野菜ですが、銀行ならばお金です。
銀行はお金がないと利益を出すことができないので、みんなに払う金利(利子)を多くすることで、みんなからお金を集めるわけです。
この金利(利子)が、いわゆる銀行にとっての仕入れ費用で、仕入れるものは「お金」であるということになります。
どんなビジネスでも、仕入れ費用がかかるのであればできるだけ安く仕入れたいですよね。
次のパートでは、銀行が「お金」を仕入れる時にどのようにして費用を抑えているか?について話していきますね。
仕入れ原価を抑える銀行


日銀や、FRBなどの中央銀行は政策金利として定めた金利で、どの金融機関にも資金を貸し出す「最後の貸し手」なんて言われます。
ちなみに、みんなが銀行に預けたときの利子ってめちゃめちゃ低いですよね?
今の日本は、ゼロ金利政策を続けているので銀行が日銀からお金を借りる時にもほぼゼロに近い金利でお金を借りることができます。
だから、わざわざみんなの預金に大きな利子をつける必要がないですね。
なぜなら、日銀からほぼ無利子状態でお金を借りれるからです。
じゃぁ、利上げした方が「銀行に預けた時の利子」がいっぱいもらえるの?
その通り!
利上げした方が、みんな利子がいっぱい貰えるんです。
でも、じゃぁなんで景気が悪くなると「利下げ」するの?ってことですよね。
みんな利子が高い方が、銀行に預金するのにね。
次のパートでは、じゃぁなぜ金利を下げるの?ということについて話していきますね。
(やっと本題です。集中!)
政策で金利を下げる意味
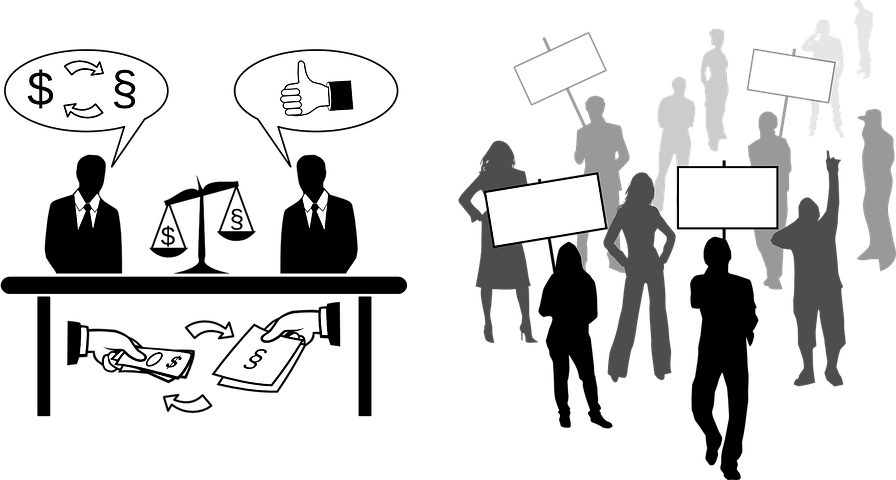
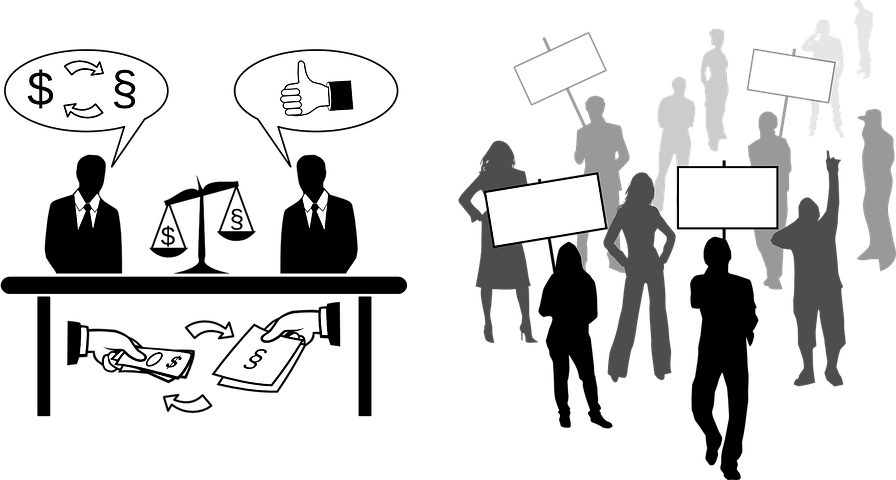
政策金利を下げるということは、民間の銀行どうしでの貸し借りをする金利も下げる効果があります。
そして銀行は、仕入れの費用に手数料を上乗せして、一般企業や個人にお金を貸し出すんですね。
だから、「仕入れの費用」が少なければ少ないほど、一般企業や個人向けに貸し出す金利も低くなるということです。
ちょっとわかりにくいかもしれませんが、簡単に言えばこうです。
日銀が金利を下げれば下げるほど、企業や個人にお金がどんどん回って経済が良くなると考えられている
家や車を買う時のローンだって、かなり低金利になっていますよね。
そうなると、みんなの買い物意欲が高まって企業は儲かりますね。
そうなると、国民も日本国家もみんなハッピーになるんですね。
計算上は、、、怖
日銀のゼロ金利の沼


日銀が世界で初めて、ゼロ金利を導入したのが1999年。
もう20年以上経過しているんですね。
ゼロ金利というのは(実質0.15%)世界史上最低の金利でした。
当時の速水優日本銀行総裁が「ゼロでも良い」と発言したことからゼロ金利政策と呼ばれるようになりました。
もちろん、金利が下がれば今までお金を借りていた人の返済する負担は減りますね。
なぜなら、払わなくてはいけない利子が減るからです。
さらには、低い金利で資金調達ができるので、新しく事業を始めたり、新たに不動産投資をしてみようとなるわけです。
だから、低金利政策というのは、経済の活性化につながると考えられています。
2008年リーマンショック
2008年、アメリカはリーマンショックによって経済が落ち込んだ時に、ゼロ金利政策を導入して最悪の状態から、アメリカ経済を持ち直しました。
また、日本ではゼロ金利を始めてちょうど20年以上経ちますが、経済が動き始めたのは、アベノミクスが始まってからです。
さらに、ゼロ金利では経済回復ができずに、マイナス金利政策を始めているのです。
わかりにくいので簡単に説明すると、もし私たちにマイナス金利が適応されると、銀行にお金を預けると利息をもらえるどころか、逆にお金を取られてしまうような政策です。
「お金を預けるくらいなら、投資とか他のことにお金を使わせて、世の中のお金の回りをよくしよう」ということです。
預金が善だと言われ続けた、日本人の考え方とは真逆ですよね。
そしてマイナス金利をしているにもかかわらず、日本の景気は目立って上向いてはいません。
日本は金利をもう下げることができないので、コロナウイルスのような異常事態が起きても金利で介入することができないということです。
今後、日本はどのように景気を回復していくのか?見守りたいと思います。
まとめ
今回は、嘘?利下げは景気後退に良い影響をもたらすのか?ということについて話をしてきました。
結論は「利下げ」は景気を刺激する(世の中にお金を回す)ことだけで、景気回復に直接つながるわけではないのが、経済の難しいところですね。
アメリカのように、目に見えて経済が回復した国もありますし、日本のように毎年のように国民の収入が毎年減ってしまっている国もあります。
「利下げ」もそうですが、無理やり景気をよくしようとしても、一筋縄ではいかないのが経済なんですね。
良い面もあれば、悪い面もある。
今の日本は、「不測の事態が起きても、金利においてはなす術なし」という悪循環に入ってしまっています。
今後の日本政府の動向に注目していきましょう!
今日も、読んでいただきありがとうございました。